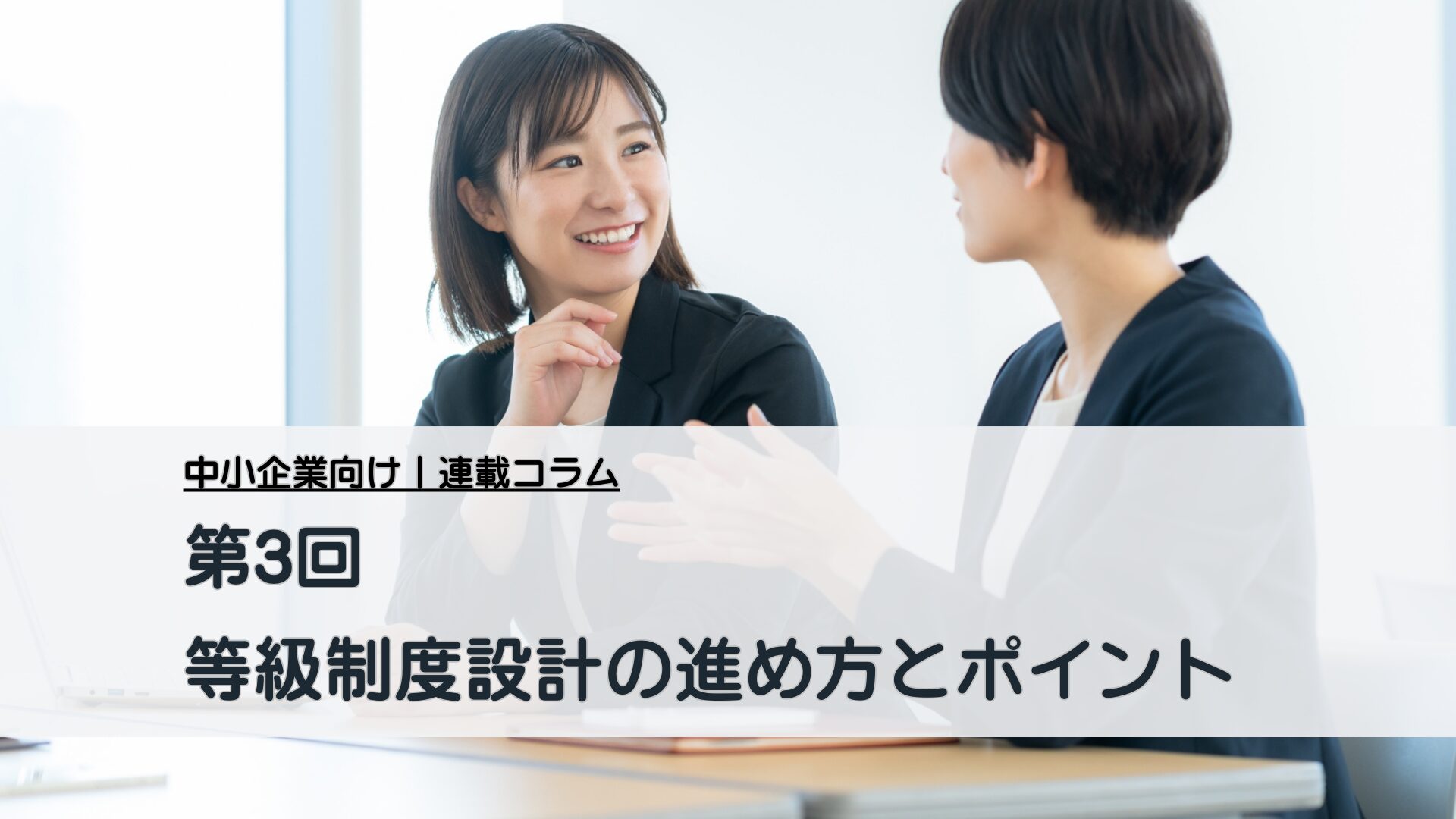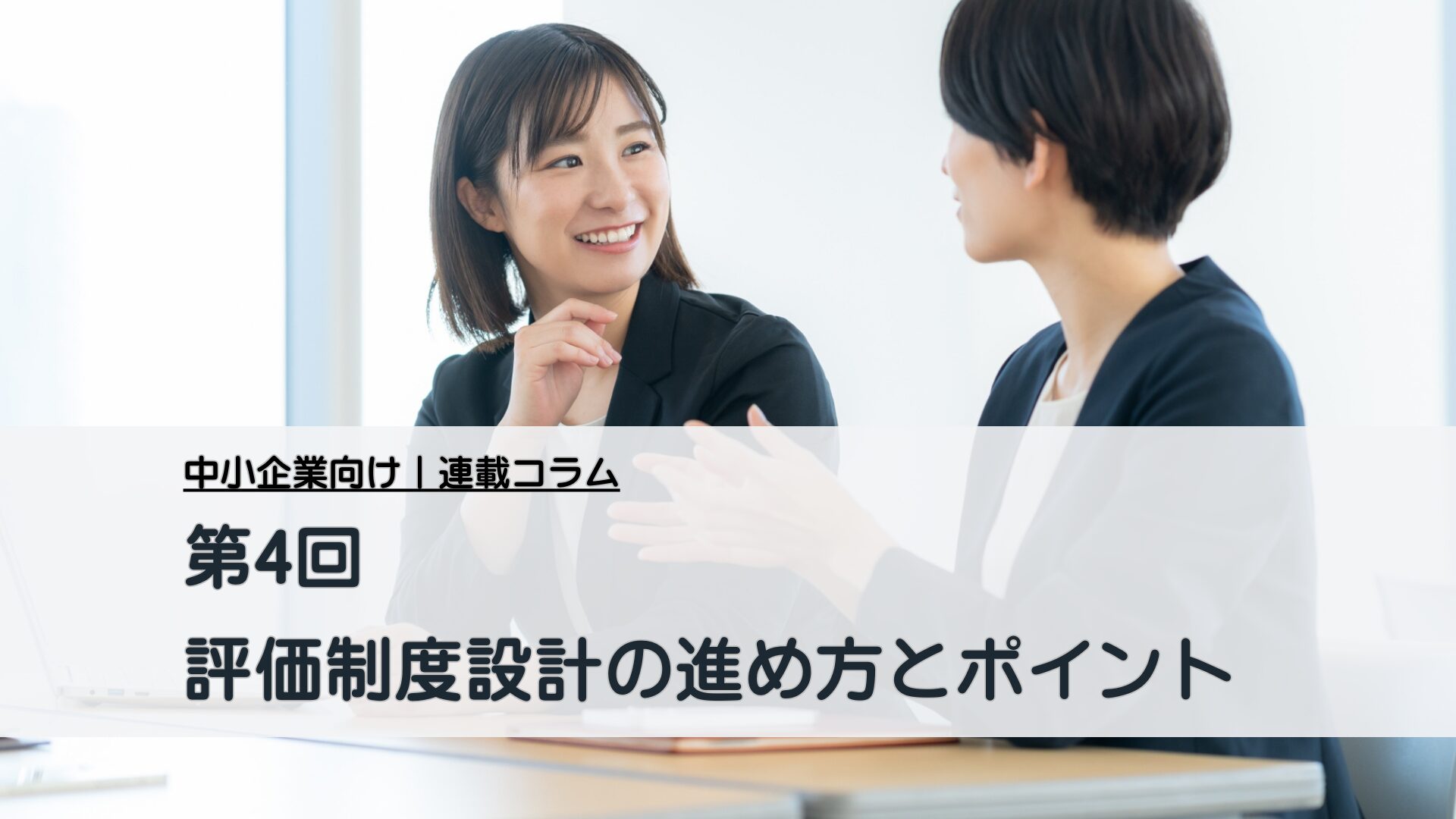第3回:等級制度の設計ポイント
本コラムは、中小企業が「等級制度」を導入・運用する際に押さえておきたいポイントを整理したものです。人事制度全体の中でも等級制度は、社員の職務範囲や役割、責任レベルを明確化する重要な役割を担います。特に中小企業においては、少人数組織であるがゆえに一人ひとりの役割が曖昧になりがちで、結果的に評価やキャリアコース設計に混乱を招くケースが少なくありません。ここでは、代表的な等級制度の種類や、それぞれを選択するときの留意点、そして具体的な等級定義のつくり方から昇格・降格の基準、教育要件に至るまで詳しく解説していきます。

中小企業向け | 連載コラム _ 人事制度設計の基本と実務ポイント
第1回 人事制度_現状分析の進め方とポイント
第2回 キャリアパス設計の進め方とポイント
第3回 等級制度設計の進め方とポイント
第4回 評価制度設計の進め方とポイント
第5回 賃金制度設計の進め方とポイント
等級制度とは何か?
職務等級制度/職能等級制度/職務・職能混合型 等、代表的な種類
職務等級制度
職務等級制度とは、「各ポジション(職務内容・役割)に対して求められる責任や難易度」をもとに等級を区分する制度です。具体的には、「営業課長」「経理リーダー」「製造ライン管理者」といった職務定義を起点とし、それぞれの職務に求められる要件を明確にしたうえで、等級を決めていきます。
職務等級制度の特徴は、職務ごとに評価基準や処遇を設定しやすい点にあります。たとえば、同じ“管理職”でも営業部門と総務部門では職務内容や市場価値が大きく異なる場合、職務等級制度なら「営業部門リーダー等級」「総務部門リーダー等級」といった形で区別が可能です。これは大企業でよく導入されている方式ですが、中小企業でも管理職の役割が明確化されている場合に有効です。
ただし、中小企業は一人が複数の職務を兼務していることが多く、職務を明確に切り分けることが難しいケースもあります。この場合、過度に職務を細分化しようとすると煩雑になり、導入コストや運用負荷が高まるリスクがあります。
職能等級制度
職能等級制度は、社員一人ひとりが持つ「能力・スキルのレベル」に基づいて等級を設定するやり方です。たとえば「課題解決力」「コミュニケーション能力」「専門技術力」などの要素を定義し、その成熟度合いに応じて等級を割り当てていきます。日本企業の多くが長年採用してきた伝統的な制度でもあり、「職能資格制度」という呼び方をされることもあります。
職能等級制度のメリットは、個人の成長ステップを見えやすくし、教育・研修プランと連動しやすい点にあります。中小企業においても、若手がどの能力を伸ばせば昇格できるのか、明確な目安を示すことができるため、人材育成の観点では有効です。
一方で、実務上の注意点としては「実際の職務内容や責任範囲と、能力要件の整合性を常にチェックする必要がある」ということが挙げられます。能力が高い社員でも、実際の役割が限定的だと十分に評価されない場合や、逆に役割を果たしていても形式的には能力要件を満たせていないと見なされるケースが出てくるため、運用ルールの徹底が課題になります。
職務・職能混合型
職務等級制度と職能等級制度の両方の特性をバランスよく取り入れたのが「職務・職能混合型」です。たとえば、一つの職務に対して必要となる能力を明確に定義しておき、かつその職務自体に求められる責任や難易度を加味した等級を設定するイメージです。
中小企業では、一人の社員がいくつもの仕事を兼務することが多いため、「職務ベースだと細かすぎるが、職能ベースだけでは現場の実態と乖離してしまう」という状況が起こりがちです。そのため、職務・職能混合型のように柔軟性を持たせつつ、社員の能力開発と職務遂行度合いの両面から評価・等級設定するアプローチは、多くの中小企業にとって導入しやすい選択肢といえます。
中小企業で選択する際の留意点(導入コスト、運用負荷 など)
中小企業が等級制度を選択・導入する際には、以下のポイントに留意することが重要です。
- 導入コストの見極め
コンサルタントや外部専門家に依頼する場合の費用はもちろん、社内の人的リソースをどの程度割けるかも含めて考えます。とくに職務等級制度を詳細に設計する場合、職務分析・職務記述書の作成などに大幅な工数が必要となることがあります。 - 運用負荷とのバランス
制度そのものを設計するだけでなく、導入後の運用プロセス(昇格審査や評価面談など)における社内負担を考慮する必要があります。制度が複雑すぎると評価者・被評価者双方が混乱し、中小企業の場合は特に機能不全に陥るリスクが高まります。 - 組織の成長フェーズに合わせる
創業間もないベンチャーフェーズと、ある程度の規模感を持ち始めた企業では、等級制度に求められる細かさや運用レベルが異なります。まずは簡易版の職務・職能混合型を導入し、企業が成長するにつれて徐々に制度を精緻化していく方法も有効です。 - キャリアコースとの整合性
前回のコラム(キャリア制度)と重複しない範囲で強調すると、マネジメントコースと専門職コースなど複数のキャリアパスを用意している場合、等級制度との連動をどう図るかが大きな課題です。制度全体が矛盾しないよう、職務・職能のどこを重視するか明確にしておくことが求められます。
等級定義の決め方
役割や求められる能力に応じた定義づくりのステップ
等級制度を導入する際に最も重要なのは、「各等級における役割」と「求められる能力・行動特性」の明確化です。以下のステップで検討を進めるとスムーズです。
- 経営方針や事業戦略の確認
等級制度は「現場がどう動けば会社の方向性と一致するか」を示すものでもあります。中長期の事業目標や経営理念を踏まえ、どのような役割を重視したいか整理します。 - 主要ポジション(職務)の洗い出し
中小企業であっても、営業・製造・管理部門など、重要なポジションを洗い出し、そこに求められるミッションや責任範囲をリストアップします。 - 求める能力・スキル項目の策定
「コミュニケーション能力」「マネジメント能力」「専門技術力」など、会社として必要な能力要素を選定します。これは職能等級制度の考え方を参考にすると分かりやすいでしょう。 - 各等級での行動・期待値の定義
たとえば、等級1は「上司の指示を理解し、自立して基本業務を遂行できるレベル」、等級2は「チームの一員として積極的に改善提案を行い、後輩の指導を一部担えるレベル」といった形で、行動基準や責任範囲を具体化します。 - 評価と賃金への接続設計
等級制度を評価制度や賃金制度と結び付けることで、社員は「この等級に上がれば、どの程度の報酬レンジになるのか」を把握できるようになります。キャリアコースにも連動させる場合は、マネジメントコースと専門職コースそれぞれで等級の定義を部分的に変えるなどの工夫が必要です。
中小企業の場合、このプロセスを一気に完璧に行うのは難しいかもしれません。まずは最重要ポジションや基本的な能力要素から着手し、後に範囲を拡大していくステップバイステップのアプローチも検討してください。
等級ごとの行動例・責任範囲・スキル要件の整理
等級ごとにどんな行動・責任・スキルが求められるのかを整理する際、以下の3つの視点を意識すると社員にとって分かりやすい等級表が作成できます。
- 行動例(具体的な業務アクション)
- 等級1:上司の指示を適切に理解し、期限までにミスなく業務を完了する
- 等級2:業務改善の提案を自ら行い、チーム内のコミュニケーションを円滑にする
- 等級3:プロジェクトのリーダーとして目標設定からメンバー育成まで一貫して管理する
- 責任範囲(どのレベルまでの意思決定や管理を任されるか)
- 等級1:自己の業務範囲に責任を負う
- 等級2:小規模チームまたはプロジェクトの進捗管理に責任を負う
- 等級3:部門全体の目標達成、リスク管理、業績向上などの責任を担う
- スキル要件(求められる専門知識・能力レベル)
- 等級1:基本的なPCスキル、ビジネスマナー、業務マニュアルの理解
- 等級2:部門固有の専門知識、問題解決能力、後輩指導スキル
- 等級3:高度な専門知識(もしくは複数分野の知識)、マネジメント能力、戦略思考
これらを明文化し、社員がいつでも参照できる形にしておくことで、評価面談やキャリア面談の際にも共通認識を持ちやすくなります。中小企業のように肩書や組織構造がフラットな場合でも、「等級表を見れば、いま自分がどのレベルで、どこを目指せばいいのか」が一目で分かるようにしておくことがポイントです。
昇格・降格基準と教育要件
昇格テスト・面接・業績評価など、多角的な評価方法の導入
等級制度を運用するうえでは、「誰がどのタイミングで、どのように昇格(あるいは降格)するのか」というプロセスの透明性が欠かせません。中小企業では経営者や上司の裁量が大きいため、属人的な判断にならないよう、複数の視点から評価を行う仕組みを整える必要があります。具体的には、以下のような方法が考えられます。
- 昇格テスト(筆記・実技)
事務系なら企画書作成、技術系なら専門技術試験など、実践力を測るテストを導入することで、客観的な基準を一つ確保できます。 - 面接評価
上長や人事担当者が等級表に基づいて質問を行い、受検者の業務理解度やリーダーシップ、コミュニケーション能力などを総合的に評価します。 - 業績評価
個人目標の達成度やチーム成果への貢献度など、定量データを用いた評価を取り入れることで、感情的な判断を抑制します。
中小企業では、こうした評価プロセスをすべて実施するのは大変かもしれませんが、少なくとも昇格面接や業績評価など、複数の要素を組み合わせることで「昇格=公正な基準をクリアした結果」という認識を社内に浸透させることが大切です。これによって社員の納得感が高まり、人事制度そのものへの信頼度も上がります。
昇格後の研修・スキルアップ支援、降格を運用する際の注意点
昇格はゴールではなく、あくまで社員の成長を一段階引き上げるステップです。中小企業でありがちなのが、「管理職やリーダーに昇格したはいいが、具体的な研修やフォロー体制がなく、結局何をすればいいのか分からない」というケースです。これではせっかくの等級制度も形骸化してしまいます。
そこで、以下のような支援策を合わせて導入することが望ましいです。
- 昇格後研修の実施
リーダーシップ研修やマネジメント研修など、役割に応じた研修プログラムを用意し、昇格した社員が新しい責任にスムーズに対応できるようサポートします。 - メンター制度やOJTサポート
既に同等級以上で経験豊富な社員がメンターとして付き、現場での実践指導を行う仕組みを作ると、実務に即したノウハウが共有されやすくなります。 - 降格ルールの明確化
万が一、昇格後に不適切な業務態度や著しい成果不振が見られた場合、降格を適用する可能性もあるでしょう。ただし、降格をあまりにも厳しく運用すると社内の士気に影響します。降格前に改善指導や再教育を行い、本人の意思確認と納得を得たうえで手続きを進めることが大切です。
中小企業では、一度役職や等級が上がると、よほどのことがない限り降格は行われないケースが多いかもしれません。しかし、等級制度の持続的な信頼性を高めるためには、「期待される役割を果たしていない場合は適切に見直す」という仕組みをあらかじめ用意しておくことも必要です。
等級制度を活かした人材育成プランの組み方
最後に、等級制度を人材育成の観点からどのように活かすかを考えます。等級制度を「評価・処遇を決めるためだけの仕組み」にしてしまうと、社員の成長を促す効果が半減します。そこで、人材育成プランを組み立てる際に以下のような活用方法を検討してみてください。
- 等級要件をベースにした研修カリキュラムの設定
たとえば等級2になるためには「論理的思考」「問題解決スキル」が必要という要件を設定しているなら、そのスキルを習得できる研修を社内外で確保し、社員が自発的に受講しやすい環境を整えます。 - 定期的なキャリア面談の実施
半年~1年ごとにキャリア面談を行い、「次の等級に上がるには何が不足しているのか」「どのような研修や実務経験が必要か」を明示します。これにより社員が現状を客観的に把握しやすくなり、モチベーション向上につながります。 - ロールモデルの設定
中小企業は大企業ほど階層数が多くないとはいえ、先に昇格した社員の事例を共有し、具体的な成功体験をロールモデルとして提示するのは効果的です。たとえば「◯◯さんは等級3に上がるために、こんなスキル開発に取り組んだ」といった実例を周知することで、他の社員も努力の方向性をイメージしやすくなります。
こうした育成プランと等級制度がしっかり連動すれば、「ただ肩書や給与レンジが変わるだけでなく、ステップアップのための具体的行動指針が得られる制度」として社員の納得と成長意欲を高めることができます。中小企業にとっては、限られたリソースの中で人材を効率よく育てるうえでも、等級制度と教育施策の連動は非常に重要なテーマといえるでしょう。
まとめと次回予告
今回は「等級制度の設計ポイント」と題して、職務等級制度・職能等級制度・職務・職能混合型など、代表的な等級制度の特徴や、中小企業が選択する際の留意点、実際に運用するうえで重要となる等級定義の決め方や昇格・降格の基準、教育要件について詳しく解説しました。等級制度は評価制度や賃金制度だけでなく、キャリア制度とも密接につながっており、社員一人ひとりの役割や責任を明確にするための“羅針盤”ともなる仕組みです。
特に中小企業では、少人数ゆえに「一人が複数の業務を担う」「役職や肩書が曖昧」という課題が生じやすく、社員のモチベーション低下や離職につながるリスクがあります。だからこそ、自社の事業戦略や経営理念、組織の成長フェーズに合わせた等級制度を設計・導入し、運用と人材育成の仕組みを連動させることが大切です。こうした取り組みを進めることで、公正な評価と処遇を実現しながら、社員の成長を後押しする強い組織づくりにつなげることができます。
次回(第4回)では、「評価制度の設計ポイント」についてご紹介します。評価の主要3要素である「成果評価」「行動評価」「能力評価」をどのように組み合わせるか、評価プロセスをどう設計すれば社員の納得感や成長を促せるのかなど、具体的な方法論を掘り下げていきます。等級制度と評価制度を連動させることで、さらに強固な人事制度を築くヒントをお伝えしますので、ぜひお楽しみにしてください。


投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。