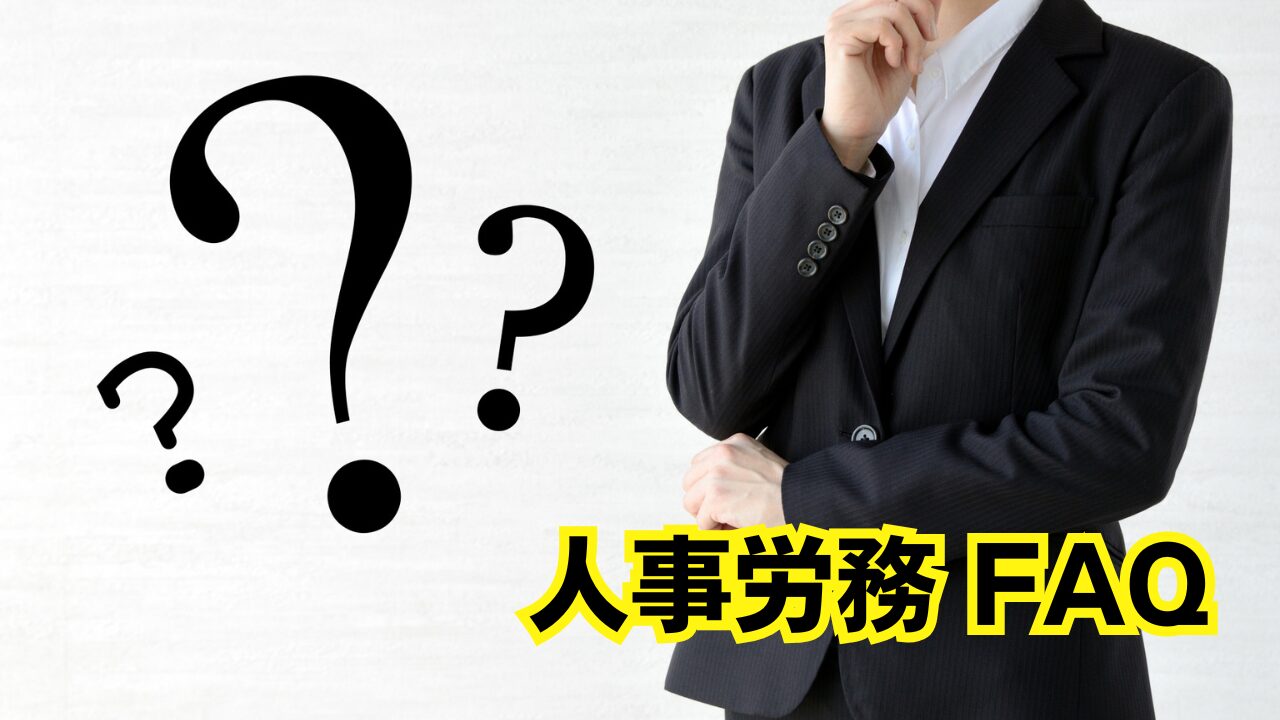「休職制度」を設けていますが、復職時の判断基準やルールをどうすべきですか?【メンタルヘルス対策と復職支援】
【結論】休職制度を設ける上で、特に復職時の判断基準やルールを明確化することは、企業の安全配慮義務を果たすために不可欠です。「①産業医または主治医による復職可能の判断」「②試し出勤(リハビリ出勤)制度の活用」「③元の部署・職務への復帰が困難な場合の対応ルール」の3点を就業規則に明確に定める必要があります。
メンタルヘルス不調による休職者が増える中、トラブルなく社員の復帰を支援し、企業の安全配慮義務を果たすための具体的な手順と、就業規則に定めるべき復職ルールを解説します。
復職判断における企業の安全配慮義務
1. 企業の義務:安全配慮義務の履行
企業には、社員の健康状態を適切に把握し、安全に働ける環境を提供する安全配慮義務があります。社員が十分回復していない状態で復職させた結果、再発・悪化した場合、企業は安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。
2. 復職の判断基準
復職の判断は、主治医の診断書だけを根拠とするのではなく、企業の指定する産業医(または医師)の意見に基づき、企業側が最終的に判断します。判断の際には、以下の点を総合的に考慮します。
- 業務遂行能力が休職前と同程度まで回復しているか。
- 休職の原因となった環境(人間関係、業務負荷など)が改善されているか。
- 適切な服薬管理、通院継続の見込みがあるか。
就業規則に定めるべき復職支援ルール
ルール1: 産業医による意見聴取の義務化
社員は復職を申請する際、主治医の診断書を提出するとともに、企業が指定する産業医または医師の面談を受けることを就業規則に義務付けます。
ルール2: 試し出勤(リハビリ出勤)制度の導入
本格的な復職の前に、短時間勤務や軽作業をさせたり、自宅で業務に関わる訓練を行ったりする試し出勤制度を導入し、徐々に業務に慣れさせる期間を設けます。これにより、再発リスクを軽減し、復職の可否を企業が実務的に判断できます。
ルール3: 原職復帰が困難な場合の取り扱い
休職の原因が原職(元の部署・職務)の業務負荷にある場合など、原職復帰が困難な場合は、配置転換を命じることがある旨を就業規則に明記します。配置転換も不可能な場合は、休職期間満了による退職とするルールも明確に定めておく必要があります。
\復職支援と安全配慮義務の体制整備を専門家がサポートします/
休職・復職に関する就業規則の作成、産業医との連携体制構築、試し出勤制度の設計を通じて、社員の健康と企業の労務リスクを両立させる仕組みづくりを支援します。