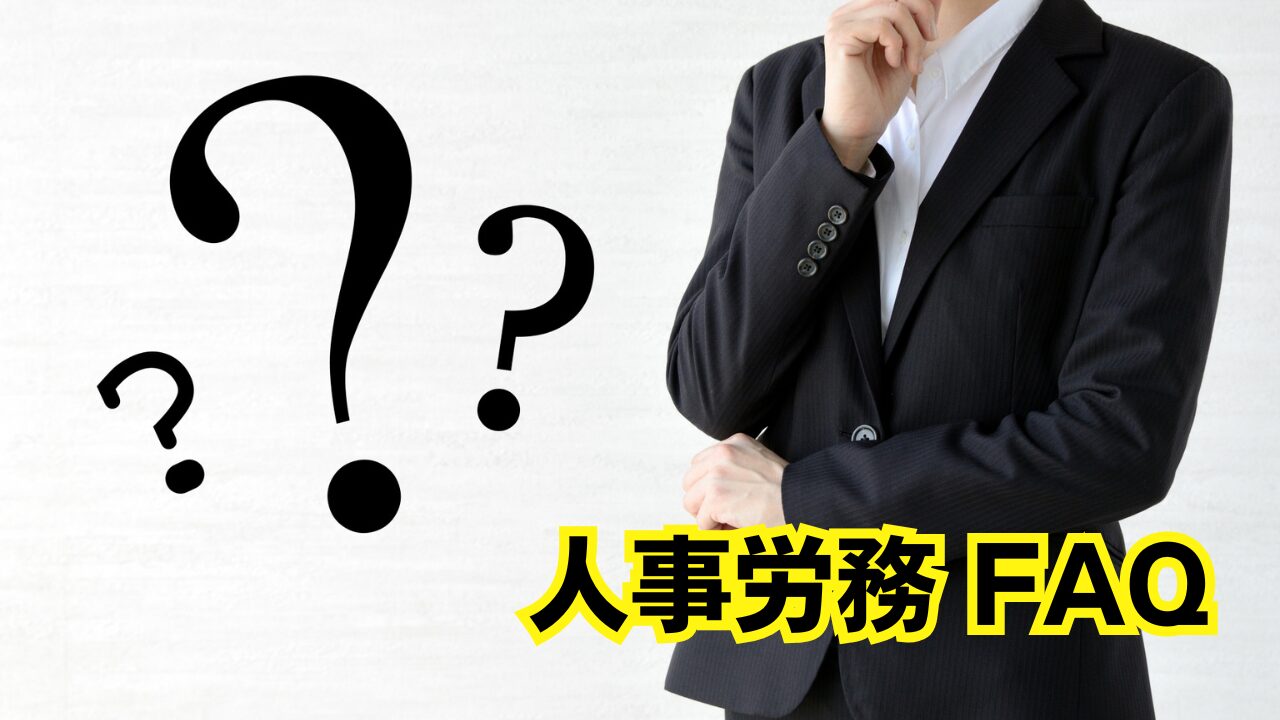退職金制度を導入・見直しする際、特に検討すべき点は何ですか?【DC/DB選択と適切な積立方法】
【結論】退職金制度の導入・見直しでは、「①制度の目的(定着 vs 確定拠出年金/DC移行)」「②原資の確保と積立方法の選択」「③税制上の優遇と法的なリスク回避」の3点を検討すべきです。特に中小企業は、将来の資金負担リスクを回避するため、外部の確定拠出年金(DC)の活用が主流となっています。
社員の福利厚生と老後の安心を支える退職金制度ですが、設計を誤ると企業の財務に大きな負担をかけかねません。制度の専門家として、退職金制度の導入・見直しにおける具体的な検討ポイントと、中小企業に最適な制度設計について解説します。
退職金制度の導入・見直しで検討すべき3つの重要ポイント
退職金制度の設計は、人事制度だけでなく、企業の財務や税務にも影響を与えます。多角的な視点が必要です。
ポイント1: 「退職金制度」の目的に応じた制度形態の選択
退職金制度には、主に以下の3つの形態があり、それぞれ目的が異なります。
- 企業年金制度(DC/DB): 確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)。福利厚生を強化し、税制優遇を受けやすい。
- 退職一時金制度: 退職時に一括で支払う。最もシンプルだが、企業が全額を負担するリスクがある。
- 中小企業退職金共済制度(中退共): 国が運営する共済制度。手続きが比較的容易で、中小企業に最も普及している。
ポイント2: 積立方法の選択と財務リスクの回避
退職金は将来の支払い義務です。特に自己都合退職の場合、企業が全てを負担する「退職一時金制度」は、業績悪化時などに大きな資金繰りリスクとなります。
- 推奨: 企業年金(DC/DB)や中退共を利用し、外部へ積立を行うことで、企業の簿外債務リスクや将来の資金負担リスクを軽減します。
- 注意点: 確定給付企業年金(DB)は、運用実績が悪化した場合、企業が不足分を補填する義務がある点に注意が必要です。
ポイント3: 現行制度から新制度への「移行措置」と法的なリスク
現行の退職金制度を改定・廃止する場合、社員の既得権を侵害しないよう慎重な対応が必要です。
- 不利益変更の回避: 退職金規程の変更は「不利益変更」にあたる可能性があり、社員の同意や労働組合との協議が必要となる場合があります。
- 過去期間の保証: 新制度へ移行する際、過去の勤続期間に対する退職金見合い額(過去勤務債務)を、新制度へ移行させるか、一時金として支払うか、ルールを明確に定める必要があります。
中小企業にとって最適な退職金制度とは?
多くの中小企業では、運用リスクが低く、税制上の優遇も受けられる確定拠出年金(DC)の導入や、中退共との併用が現実的で推奨されます。
退職金制度は、賃金制度、人事評価制度と総合的に連動させる必要があります。例えば、「評価の高い社員はDCの掛け金を増やす」など、人事戦略と連携した制度設計が可能です。専門家にご相談いただくことで、税理士や社労士ではカバーしきれない、人事戦略に基づいた制度設計が実現できます。
\企業の財務リスクを抑え、社員の安心につながる制度設計を/
複雑な退職金制度の導入・見直しは、人事・労務・財務の専門知識が必要です。貴社の資金計画、人事戦略に合わせた最適な制度の選択と、スムーズな移行手続きを支援します。