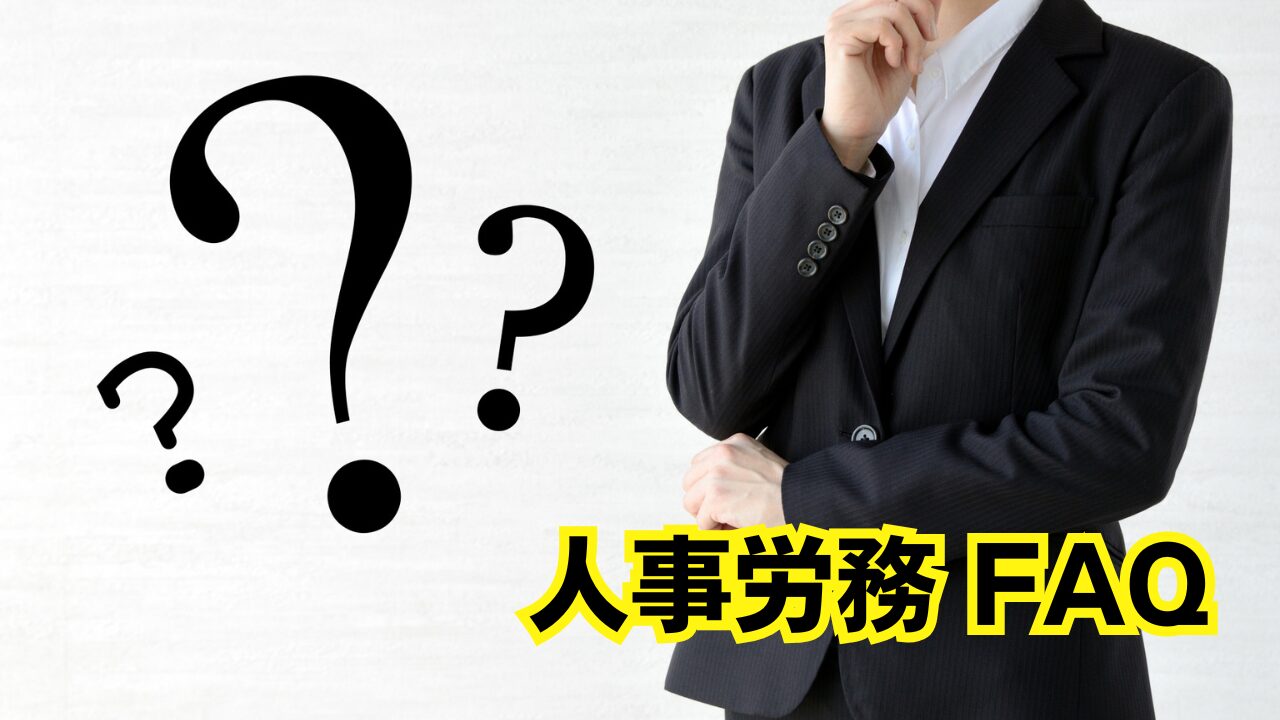ハラスメントが発生した場合の適切な対応手順は?【中小企業向け 法的リスク回避と実務対応】
【結論】ハラスメントが発生した場合、企業は「①相談窓口の一本化と迅速な事実確認」「②被害者・行為者双方への適切な措置とフォロー」「③再発防止のための啓発・研修」の3ステップを、公正かつ秘密を厳守して行うことが法的に義務付けられています(パワーハラスメント防止法)。対応を誤ると、企業の信頼喪失や損害賠償リスクにつながります。
中小企業においても、ハラスメント対応は重要なコンプライアンス課題です。本記事では、ハラスメントの定義から、実際に問題が発生した際の具体的な対応手順と、法的リスクを最小限に抑えるためのポイントを解説します。
ハラスメントが発生した場合の適切な対応手順3ステップ
厚生労働省の指針に基づき、企業は以下の手順で速やかに、かつ公平に対応する必要があります。
ステップ1: 相談窓口の一本化と迅速な事実確認(ヒアリング)
- 窓口の設置: 相談窓口(例:人事担当者、外部の社労士)を一本化し、周知徹底します。
- ヒアリング: 被害者、行為者、目撃者など関係者から個別に、秘密厳守で事実関係をヒアリングします。事実確認は慎重かつ客観的に行い、感情論を排します。
- 記録の徹底: ヒアリング日時、場所、内容、発言者などを詳細に記録します。
ステップ2: 被害者・行為者双方への適切な措置とフォロー
事実関係が確認できた場合、行為者と被害者の両方に対して、再発防止と職場環境維持のための措置を講じます。
- 行為者への処分: 就業規則に基づき、懲戒処分(厳重注意、減給、出勤停止、諭旨解雇など)を決定・実行します。
- 被害者への配慮: 部署異動、勤務場所の変更、メンタルヘルスケアの提供など、被害者の心身の健康を回復させるための措置を講じます。
- 報復的措置の禁止: 行為者による被害者への不利益な取り扱い(報復)を厳に禁止し、モニタリングします。
ステップ3: 再発防止のための研修とルールの再徹底
ハラスメント対応は、個別事案の解決だけでなく、組織全体の再発防止に繋げる必要があります。
- 全社研修: 管理職向け、一般社員向けに分けて、ハラスメントの定義、影響、防止策に関する研修を定期的に実施します。
- ルールの明確化: ハラスメントに関する就業規則や相談対応フローを再点検し、周知徹底します。
中小企業がハラスメント対応で陥りやすいリスクと対策
中小企業では、人事担当者が一人で対応を抱え込んだり、経営者と行為者の関係が近いために公平性を欠いたりするリスクがあります。
- 公平性の確保: 相談窓口を外部の専門家(社会保険労務士など)と連携させ、客観的かつ公平な視点で事実確認を行える体制を構築することが推奨されます。
- 就業規則の整備: ハラスメントの種類(パワハラ、セクハラ、マタハラなど)と懲戒処分を明確に定めた就業規則の整備は、法的なリスク回避の基礎となります。
\ハラスメントリスクを未然に防ぐ、強固な労務管理体制を構築しませんか?/
当社は、就業規則の見直し、ハラスメント研修の実施、外部相談窓口の設置支援を通じて、貴社のコンプライアンス強化と、社員が安心して働ける職場環境づくりをサポートします。