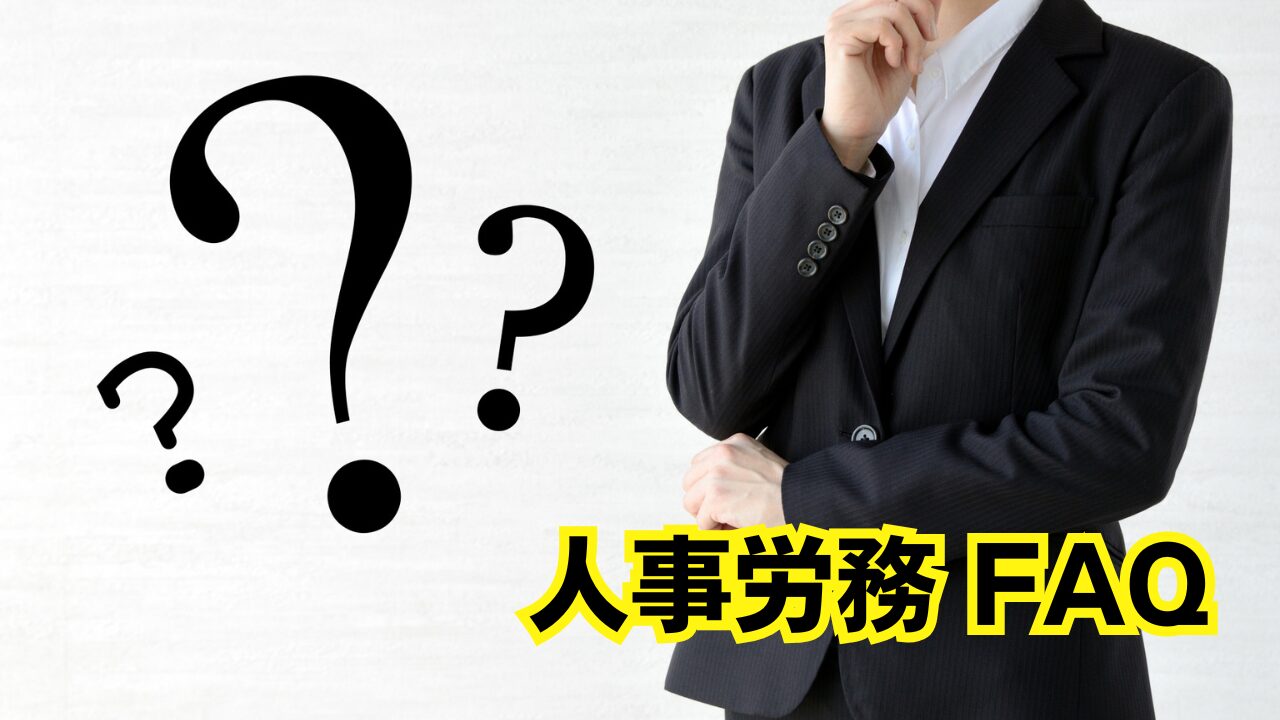社員を解雇したい、または退職勧奨したい場合の、法的に正しい手順は?【中小企業の労務紛争回避】
【結論】社員の解雇は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ無効と判断される(解雇権濫用の法理)ため、極めてハードルが高い行為です。企業が取るべき手順は、「①退職勧奨(合意解約)による円満な解決を試みること」が最優先です。解雇に踏み切る場合も、「②30日前の解雇予告と③退職金・賃金の支払い」といった法的手続きを厳格に遵守する必要があります。
社員との雇用契約の終了は、中小企業にとって最も重大な労務リスクです。法的紛争を回避し、円満に解決するための正しい手順と、解雇の厳しい要件を解説します。
解雇と退職勧奨の法的違いとリスク
1. 退職勧奨(推奨されるアプローチ)
- 法的性質: 企業が社員に退職を促し、社員の合意を得て雇用契約を終了させる合意解約です。
- メリット: 社員の合意があれば、解雇権濫用の法理に問われるリスクがなく、最も安全かつ円満な終了が可能です。
- 注意点: 強制や威圧的な言動は不法行為となり、後から社員が「不当な退職勧奨だ」と訴えるリスクがあります。
2. 解雇(最終手段)
- 法的性質: 企業が一方的に雇用契約を打ち切る行為です。
- ハードル: 解雇権濫用の法理により、裁判で解雇が無効と判断される可能性が非常に高く、無効とされた場合、解雇後の賃金全額の支払い(バックペイ)を命じられます。
退職勧奨・解雇の正しい手順
手順1: 事前準備と改善指導(解雇回避努力)
解雇の理由が社員の能力不足や勤務態度にある場合、解雇を回避するための以下の努力を行った証拠が必要です。
- 指導記録の作成: 改善指導を複数回実施し、その内容や社員の反応を詳細に記録します。
- 配置転換の検討: 他部署への配置転換など、解雇を避けるための手段を検討・実行した事実を作ります。
手順2: 退職勧奨の実施(合意を目指す)
- 面談: 複数回の面談を通じて、退職の必要性を説明し、退職金の上乗せや再就職支援といった優遇措置を提示し、社員の自主的な退職の合意を得ることを目指します。
- 合意書の作成: 合意が得られた場合、必ず「労働者本人の自由な意思による合意解約である」ことを明記した合意書(退職届)を作成し、双方署名・捺印します。
手順3: 解雇予告と金銭支払い(解雇の場合)
- 解雇予告: 解雇日の30日前までに社員に予告します。
- 解雇予告手当: 予告期間が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払います。
\解雇・退職勧奨は、専門家の介入で労務紛争を回避できます/
雇用契約の終了は、初期対応を誤ると裁判につながります。社員とのトラブルを未然に防ぎ、法的に安全な手順で雇用契約を終了させるための手続き支援を専門家がお手伝いします。