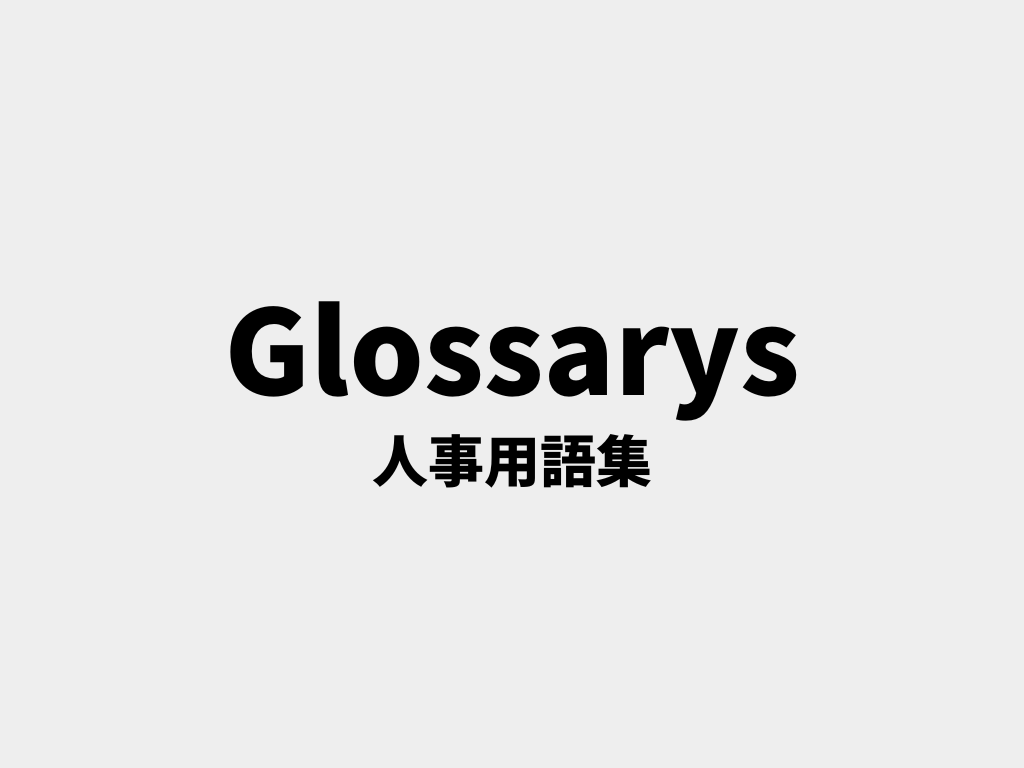ジョブ型雇用とは?【中小企業が導入するメリット・デメリットと注意点】
【定義】ジョブ型雇用とは、職務内容、勤務地、労働時間などを採用時に明確に限定し、その職務遂行能力(ジョブ)に対して報酬を支払う雇用システムです。社員は職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)に定められた範囲の責任を負い、その専門性を追求します。
近年、大手企業で導入が進むジョブ型雇用ですが、中小企業にとってはどのような意味を持つのでしょうか? 従来のメンバーシップ型雇用との違いを踏まえ、導入時のメリットと注意点を解説します。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い
従来の日本企業で主流だったメンバーシップ型雇用と対比することで、ジョブ型の特徴が明確になります。
| 項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用(日本型) |
|---|---|---|
| 採用基準 | 特定の「職務」に必要なスキル・経験 | 職務を限定せず、ポテンシャル(可能性) |
| 報酬の決定要因 | 職務の価値、職務遂行能力 | 年齢、勤続年数、能力、学歴 |
| 人事異動 | 原則なし(職務の範囲内) | あり(会社が必要とすれば異動) |
| 評価制度 | 職務目標に対する成果 | 職務遂行能力、プロセス、情意 |
中小企業がジョブ型雇用を導入する際のメリットと注意点
メリット1: 専門性の高い人材の確保
職務内容と報酬を明確に提示することで、特定の専門スキルを持つ人材や、キャリア志向の明確な中途採用者にアピールしやすくなります。
メリット2: 人件費の最適化
年齢や勤続年数に関係なく、職務の価値に応じて報酬が決まるため、人件費を効率的に管理できます。
中小企業が失敗しないための注意点
- ジョブ・ディスクリプションの明確化: 職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)を詳細かつ明確に作成する労力が必要です。これが曖昧だと、トラブルの原因になります。
- 評価制度との連動: 職務目標に対する客観的な成果評価が必須です。従来の曖昧な評価制度では機能しません。
- 法的なリスク: 労働契約法に基づき、職務が限定された社員の同意なく配置転換することは難しくなるため、人事の柔軟性が低下します。
\ジョブ型移行の成否は、賃金・評価制度設計にかかっています/
ジョブ型雇用への移行を検討されている場合、賃金体系や評価基準の抜本的な見直しが必要です。貴社の事業に合った制度設計を専門家が支援します。