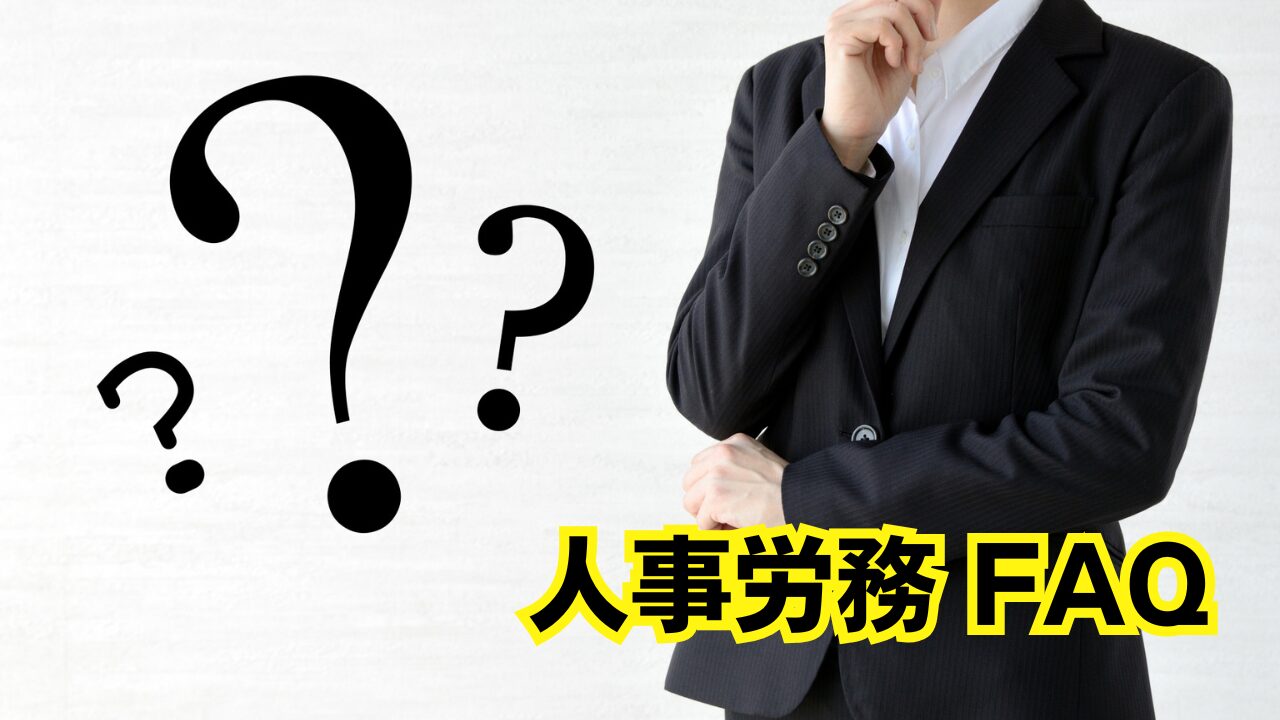社員の給与がバラバラ?統一的な賃金テーブルを作る3ステップと中小企業での注意点
【結論】社員の給与のバラつきを解消し、統一的な賃金テーブルを作成するためには、「等級制度の設計」「賃金水準の決定」「号俸(昇給カーブ)の設定」の3ステップが基本です。特に中小企業では、外部水準に依存しすぎず、自社の支払能力と求める人材像に基づいた設計が成功の鍵となります。
「給与の決め方がブラックボックス化している」「中途採用者の前職給与に引きずられ、既存社員の不満が高まっている」――。このような状態は、組織の士気を下げます。社員が納得し、成長意欲につながる賃金制度を構築するための具体的な手順を解説します。
なぜ中小企業の給与はバラバラになりがちなのか?
原因1: 場当たり的な採用・昇給決定
創業期や急成長期にある中小企業では、採用時の交渉や前職給与を基準に給与が決まってしまうケースが多く見られます。その結果、入社時期や交渉力によって同じ仕事内容でも給与に大きな差が生じ、既存社員から「なぜあの人の方が高いのか」という不満が発生します。
原因2: 明確な等級制度の欠如
賃金テーブルを支える土台となるのが「等級制度」です。この等級制度(=社員に求める能力や役割の基準)が曖昧だと、「この仕事はいくら払うべきか」「どのレベルで、何を達成すれば昇給するのか」という共通ルールがありません。結果として、社長や特定の管理職の主観で昇給が決まり、不透明な運用になってしまいます。
統一的な賃金テーブルを作成する基本の3ステップ
ステップ1: 評価制度と連動した「等級制度」の設計
- 企業規模と事業内容に合った等級(ランク)を設計します。
- 等級制度は、職務(ジョブ型)と能力(メンバーシップ型)のどちらを重視するかを明確にし、社員に「この等級に上がるためには、何を達成すべきか」という目標を示します。これが賃金テーブルの縦軸(等級)となります。
ステップ2: 賃金水準(レンジ)の決定と相場の調査
- 設計した等級ごとに、最低額(下限)と最高額(上限)となる賃金レンジを決定します。
- この際、厚生労働省の統計や地域相場(例:広島県内の同業他社の水準)を調査しつつ、自社の支払能力と経営戦略を踏まえた独自の水準を設定します。
- 外部の相場に引っ張られすぎて、無理な制度設計にならないよう注意が必要です。
ステップ3: 昇給カーブ(号俸)の設定と運用ルールの明確化
- 等級内で給与がどのように上がっていくかを示す号俸(昇給カーブ)を設定します。
- 昇給は、単なる勤続年数ではなく、人事評価の結果と連動させることが重要です。
- 賃金テーブルが「賃金規程」として法的に有効となるよう、移行措置や運用ルールを明確に定めます。
中小企業が賃金テーブル導入で失敗しないための注意点
賃金制度の設計は、社員の生活に直結するため、非常にデリケートな作業です。特に中小企業では、既存社員への影響を最小限に抑えるため、以下の点に注意が必要です。
- 複雑化の回避: 大企業のような細かすぎる等級・号俸は避け、シンプルな設計を心がける。
- 移行措置の慎重な設定: 現行給与と新テーブルの差額を調整するための猶予期間や調整手当を設ける。
- 社員への丁寧な説明: 制度導入の目的(例:公平性、成長への期待)を社長自身が社員に丁寧に説明し、納得感を得る。
賃金制度の設計・見直しは専門家にご相談ください
賃金制度の設計は、法令遵守はもちろん、社員のモチベーションや経営の安定性に直結する経営戦略そのものです。
当社は、中小企業の「攻め」と「守り」を両立させる賃金制度の設計を得意としています。場当たり的な給与決定から脱却し、社員が納得して働ける公平な仕組みづくりをサポートします。
\「なんとなくの給与決定」から脱却しませんか?/
公平で透明性の高い賃金制度は、社員の定着率向上と採用力の強化に直結します。貴社の経営状況と、社員に求める役割に応じた最適な賃金テーブルの設計を支援します。